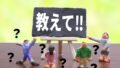教えすぎ、というテーマで日記にしたが、今度は受け取る側、勉強する側である子供の話。
教えられすぎるのに慣れていると、自分で考えることがおろそかになる。多くの人が同じことを言っているが、それはとりもなおさず真実だからであって、勉強ができるようになるのは、自分で考えて進めていくときである。その当たり前にどうすれば到達できるのかが問題なのだが、そのための前提の一つが、子供に考えて聞く力があるか否かだ。
よほど変な先生でない限り、教わった瞬間は大半の子がわかる。大事なのはその次で、教わってわかったことを自分のものにしにいく段階だ。それが復習だ。私も学校復習を進めてもらう段階では、こちらから教え直すことは少ない。学校で授業を受ける、学校で練習をする、場合によっては宿題が出るのでそれをやる、これらを通じて授業を理解できたか、理解に穴があればそこを埋め、理解が完璧であれば発展的な話をする。これが私の思う理想的な復習だ。
これが出来上がるには、子供たちに「考えて理解する」気持ちが必要だ。これがないと、延々と「わからないから教えてほしい」を連発することになる。もちろんわからないから教えてほしい、と思うことは何も間違っていないのだが、この教えてほしいの部分が、その場を何とかクリアしたいだけになってしまうことが問題なのだ。多くの末路は、試験前になっても同じ内容で「わからないから教えてほしい」を繰り返し、理解を自分でしようとしないまま試験に突入。当然理解はしていないからその部分はとれない、という結果だ。
だから私は、教えるたびに言い続ける。
「人に聞いても、答えを見てもその場は誰でもわかる。それを自分の中で何度も考え直して、同じ問題を自分の頭で考えて、解き方を組み立てて、組み立てた解き方に従って解けている。その答えが間違いなく正解になっている。そういう状態になっているかを確認しなさい。それができないといつまでたっても『わからん、教えて』っていうようになる。テストになってもわからないまま。まずは自分でできるようになるために考えなさい。」
教えてもらうだけではできるようにはならない。私が言っても説得力がないなら、「学びて思わざれば則ち罔し(くらし)。」(論語)と孔子が言っている。