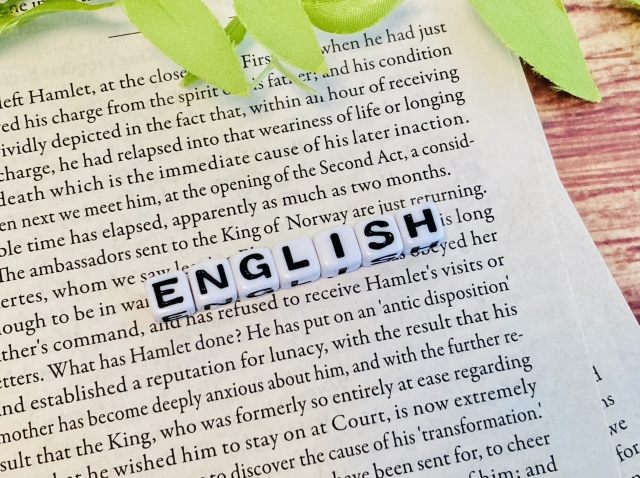先日の話だが、中学1年生に学校の授業の様子を聞くことにした。いつものように「何やったん?」と授業進度や内容を聞くのとは異なり、先生がどんなふうに話をしてくれているのかを尋ねてみようと思ったわけである。
いろいろな話をしてくれたのだが、とりわけ皆がわかりにくいと話していたのは英語だった。どの中学の子も英語だけは必ず口に出していた。
そのうちの一人のいわく、「教科書の本文をスクリーンに映しながら、意味を言っていくだけ。途中でとある文を指して『ここは命令文といいます』と紹介された。」とのこと。
私が尋ねる。「で、『命令文ってこういう風に作るんやで』とか『動詞の原形っていうのはね』とかを教えてくれるわけやね?」。その子は首を横に振った。
もうこの時点で、私の頭の中は漫画やアニメよろしく巨大な?マークでいっぱいなのだが、もう一人の子(別の中学)にも同じように尋ねる。
その子のいわく、「命令文の話はしてくれた。ただ、動詞の原形って何なのかの説明はしてくれなかった。」だそうだ。
これだけを話すと、先生の悪口を言っているように聞こえるかもしれないが、問題はそこではないと思っている。何度か話してきたが、問題は英語の教科書の中身だ。単元の配列の仕方だ。先生の立場から見ても、この教科書はとにかく教えにくい。現場の英語の先生方のご苦労はいかばかりかと拝察する。
例えば動詞の原形って何?ということになれば、3単現のsや-ing形のように、英語の動詞は様々に変化形があるということを前提にしなくてはいけない。だから、我々のころの中1英語の教科書は(NEW CROWNだったと思う)、動詞の原形が絡む助動詞であるcanを習うのは、最後から2番目の課だった。それまでに3単現や進行形は習得済みの段階だ。命令文もその少し前くらいの課で習った。「動詞の原形」を教えやすい配列にしていたということだろう。
今は全く違う。尼崎で採択しているHere We Go!では、Unit1の段階でcanも扱う。canの後ろが動詞の原形である、とこの段階で教えても、主語がIかYouの文しか知らない生徒にとっては、canがあるなしに関わらず動詞は同じ形だから、一緒くたになるだけだ。「ああ、動詞の前にcanをつければ「~できる」なのね」で終了だ。
仕方がないので、生徒たちに聞いた。「学校でやった文法の話を、俺から改めて授業の形で説明してほしいか?」全員が首を縦に振った。今までは個々に聞き取る形で進めていたが、全員が学校授業で習得できづらい状況に置かれている今、こちらも教え方に変化が必要なようだ。
隣にいた中2生にも「同じようにやるで」と予告した。授業の在り方については昨日も日記にしたが、実情に応じて塾は、塾の授業は在り方を改めねばならぬ。
来週からの授業の内容が固まった。