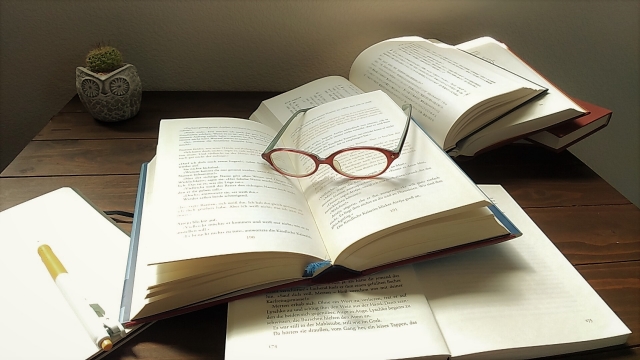中3生の一人に、読書が大好きな子がいる。前に塾に来た時、読んだ本やYouTubeなどで朗読を聞いた本の話をいろいろしてくれた。
私個人もそうだったのだが、高校3年の大学受験生だった時、どんなに勉強が忙しい時でも、読書の習慣だけは切らさなかった。高校や予備校の行き帰りの電車や寝る前など、隙間を見つけて本だけは読んだ。
読書が勉強にどんな効果をもたらすか、といった話をしたいわけではないが、私の経験上、言えることがある。それは、「勉強できる子は読書する子が多い」ということ。そしてもうひとつ、「読書する子が勉強できるとは限らない」ということ。一見相反しているように見えるが、肌感覚として確信している。
まず、勉強ができる子の読書とできない子の読書は差がある。心に強烈に思っているわけではないが、できる子は読書から勉強している。できない子は読書から娯楽しか得ていない。同じ本を読んでも、「楽しかった」で終わるか、「そうか、こういう風に考える人もいるのか」と思うかで、すでに差がある。それがミルフィーユのように幾重にも積み重なってその子の知識になる。教養になる。もっと言えばその子の「個」になる。
もちろん、娯楽のために本を読むことを否定しているわけではない。ただ、できる子というのは、娯楽の中にも知識や教養の種を見つけ出すことに長けている。
読書に限った話ではないだろう。ゲームであってもYouTubeなどの動画であってもいい。多くの子が娯楽としてしか消費しないものの中にあっても、ゲームの攻略の中から得られるもののように、経験を自分の血肉に変えられる資質こそ、勉強ができる子に備わる資質と言っていいかもしれない。
では、そういうものがなかった我が子はどうすれば?と考える人もいるかもしれない。もちろん小さいころからそういう経験を培った子と比べれば、不利な条件からのスタートであることは覚悟したうえで、日常から学びを得られるヒントのようなものを与えていくことから始められてはいかがだろうか。身につく可能性は低いがゼロではない。もし小学、中学生のうちに身につかなかったとしても、将来に身につく種にはなるかもしれない。
取り留めない話になったが、「読書してればOK」という考え方は間違い。もしも読んで勉強する資質に目覚めてほしければ、一緒に読んであげていろんなことを問いかけてあげてみるといいかもしれない。