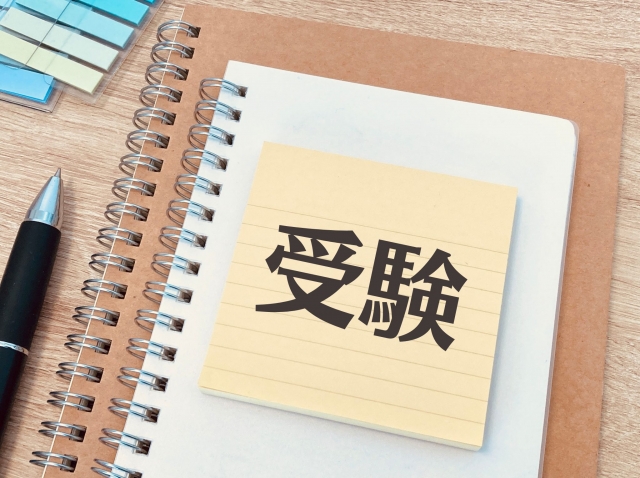昨日の続き。
まずは理科。例年と大きく変わる問題は少なかった。一番最後の電流の問題が少し難しかったか。サンドスイッチの回路や一番最後の計算は、慣れていないと難しかったろう。そもそもだが、昨日も言った話だが兵庫県の理科は難しい。大きな理由として小問集合(数学の大問1のような、基礎問題を大量に出す大問)がないことが挙げられる。いきなり実験や観察が始まり、流れに従って問題を解くという標準的な理科の問題が始まる。しかもこれが生物地学物理化学の各分野で中問2題、計8題になるので時間も厳しい。みんなが簡単に取れそうな問題が少ないのだ。ただ、一つ一つの問題を丹念に見ていけば、定期テスト~応用レベルの標準的な出題が大半を占めていることに気づく。普段から定期的に理科の復習ができ、各出題パターンに対する理解ができていれば、高得点も望める科目である。まあそれが難しいのだけれども。
そして英語。番組でも解説されていた通り、語彙レベルがかなり高い。出題形式などに大きな変化はないが、素材そのもののレベルが上昇した印象だ。従来、兵庫県の英語は易しいのだが、これからこのようにレベルを上げてくる可能性もありそうだ。問題そのもののレベルは、落ち着いて読めればしっかり得点できるものがそろっている。和訳や英作文が課されない分、選択肢を丹念に読む意識がないと、ごっそり失点する恐ろしさは国語と同様だ。
最後に全科目にわたる概観。番組でも語られていたが、公立高校入試は「大学入学共通テスト」を強く意識して作問されている。共通テスト導入からもう5年以上経つのに、と思う向きもあるかもしれないが、今年は共通テストが改定される年にあたる。試験科目に「情報」が追加されたり、各科目ともマイナーチェンジが施されている。大学入試を強く意識した出題を改めて意識する契機になったことだろう。そのせいか、各科目とも問題で使う知識に変化はないものの(当たり前か)、背景知識や社会情勢、科目を横断する問題意識など、勉強というより学問に対する意識を強めた問題に変化を見せつつある。私としても、単なる「お勉強」にとどまらない学びをどのように提供できるか、取り組みを考えねばならないと改めて思った。
発表は19日の水曜日。吉報を待つのみである。