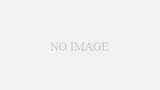3月を迎え、3学期もいよいよ終わります。
春休みを過ぎると、新学年、あるいは進学により新しい学校生活が始まります。
そんな中、何でこんなタイトルでお話をするの?となりそうですが、今回は「成績が落ちる、あるいは伸び悩む生徒さん」にありがちな特徴をお話しします。ありきたりなテーマをはじめ、傾向についていくつかご紹介します。
①勉強の仕方をわかっていない
進級よりも、進学(小学→中学、中学→高校)のタイミングでよくある傾向です。
小学校、中学校、高校では、勉強の内容やレベルが異なるのはもちろんですが、何より大きく異なるのは、各科目の勉強法のアプローチです。
一口に勉強の仕方と言っても、魔法のような万能なものはありません。いきなり全力で「〇時間勉強するぞ!」というわけにもいきませんし、「とにかく問題集を大量に購入してやってくぞ!」というわけにもいきません。
一人ひとり性格や学力などの能力、得意分野や苦手分野、目標地点が異なりますから、様々な方法を試しながら、その人に一番合った方法を探していく必要があります。
②(①に関連して)他人の勉強法ばかり研究する
これはどちらかというと高校生に多いかもしれません。もしくは中学受験している小学生の保護者の方にも多い傾向があります。
近年はYouTubeなどで「勉強法」「参考書紹介」「〇〇大生の受験時代のルーティーン」などの勉強にかかわる動画コンテンツが非常に多く配信されています。私も話のタネに見ています。
私たちのころはYouTubeはおろかネット環境もあまり普及していなかったので、例えば「東大合格者の勉強法」みたいなタイトルの書籍で研究する人が多かった記憶があります。ですから、「今の時代はええなあ」なんて思ってしまいます。もちろん、この書籍だって今でもたくさん出版されています。
しかし、この「情報ばかり追い求める傾向」には注意が必要です。
理由は「情報」にはありません。配信者や出版社はでたらめでやっているわけではありませんし、紹介されている内容も至極真っ当な内容がほとんどです。
問題なのは「姿勢と時間」です。
まずは姿勢について。「情報」に踊らされる人というのは、私の完全な偏見ですが「他人任せ」な傾向が強いように思います。自分の意志がない、あるいは弱いため、「この人のやり方を見てみよう」「あの人のやり方も見てみよう」ということになるのです。そのうえでもしうまくいかなかった場合、「あの人のやり方は合わなかった」「この人のやり方の方がよかったかも」「あの参考書じゃ伸びなかった」「この参考書の方がいいかもしれない」と考え、次なる「情報」に飛びつくものです。こういう人はまあ伸びません。点数や偏差値の伸び悩む理由の中に「自分が悪い」という反省が欠けているからです。ここで勉強法や参考書のせいにしてしまう人ははっきり言ってダメです。
もう一つの「時間」について。これは単純明快。「そんな情報ばっかり調べてる時間に問題集の1ページでも進めたらどうやねん!」ということです。あまりに簡単に言い過ぎなので補足すると、「情報を調べたり分析しただけで勉強した気になる、勉強できた気になる」というのが問題なのです。成績が上がる仕組みについては改めてお話ししますが、簡単に言うと「自分で考えて問題が解ける」瞬間に学力は向上します。そうすると、大事なのは「自分で取り組む時間がどれだけかけられているか」なのです。その時間を削るだけでももったいないのに「できた気になる」なんてただの間抜けです。同じ時間があるなら、いっそゲームでもして気分転換した方がましです。
最後に。私は「勉強法」などのコンテンツが害悪だなどとは思っていません。適切に取り入れれば大きな効果を発揮する可能性すらあると思っています。あくまで私が批判するのは「そういう情報ばかり見て勉強できた気になる」姿勢にあります。
まとめ
特に2番目の「勉強法」中毒は問題です。今のように情報過多な世の中だからこそ、情報ばかりに踊らされない姿勢が大切だと思います。
におか塾は、「ハイレベルな勉強がしたい」、「難関高校進学を目指したい」尼崎の少人数指導学習塾です。
ぜひお電話(06-6415-7898)、メール(niokajuku2021@gmail.com)、お問い合わせページまで!